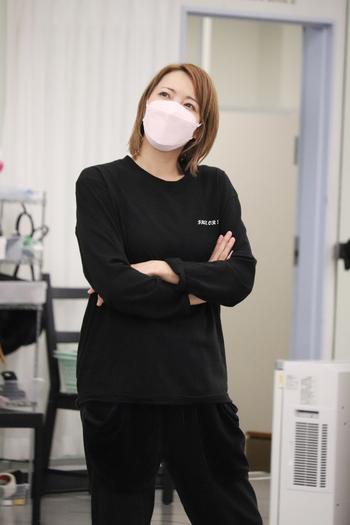演出家・小林香が2010年より作り続けているショー・ステージ「SHOW-ism」シリーズの最新作『BERBER RENDEZVOUS』が11月20日(日)から上演される。歌とダンスをふんだんに盛り込みながらも、単なるコンサートあるいはミュージカルでは終わらせず、ストーリー性のあるショーの中で俳優自身の持つ輝きを一層際立たせ、好評を博してきた当シリーズ。第11弾となる今回は、柚希礼音、美弥るりかをはじめとする11名のレギュラーキャストと豪華日替わりゲスト、オールフィメールで挑む新作。内容は"映画愛"に満ち満ちたものになりそうで......。11月某日、その稽古場を取材した。
物語は、新作映画を撮るために11人の女性が集められたところから始まる。パリで撮影のはずが、気付いたらそこはサハラ砂漠。彼女らに課せられたミッションは、2週間で「人間とは何か」をテーマにした映画を1本撮ること。タイトルは『ベルベル・ランデヴー』。報酬は超高額。初対面の者、面識のある者、一方的に銀幕で見ていた者、関係性はそれぞれだがお互いをコードネームで呼び合い、急ごしらえのチームとしてこの仕事に取り掛かることに......。
この謎めいたミッションの目的は一体何? というハテナもこの物語を貫く大きな軸なのだが、なんと取材日の稽古はその謎が明かされるシーンど真ん中。演出の小林からは「(ネタバレしないように)うまいことレポートお願いしますね!」と、こちらまで重大ミッションを課せられてしまった。おそるおそるレポートを進めてみよう。舞台面にあたる場所にはホリゾント幕になるのだろうか、白い大きな幕が設置されているだけのシンプルなセット。あるいはこれが銀幕になったりもするのかしら......? 「SHOW-ism」シリーズは演劇作品としてはかなり早い段階でプロジェクションマッピングを取り入れたりと、映像の使い方も印象に残るものが多い。そのため想像は膨らむが、答え合わせは本番の楽しみにとっておこう。
どうやら彼女らが撮る映画は、オムニバスで様々な人間の姿を描いていくものになっている模様。この日、まず稽古にあたっていたのはその短編映画のひとつ、柚希、美弥、原田薫、JKim(この日の稽古は欠席)の4人を中心としたドラマ。祖母、娘、孫の三世代の歴史と思いが紡がれる内容だ。劇中劇シーンは華やかに魅せるものも多いが、ここはずいぶん"芝居"に寄った一幕だ。祖母役の原田が、孫娘役の柚希の背中を送り出すように押す、というアクションひとつとっても、どういう気持ちからその行動をとったのかを原田と小林が丁寧に話し合っている。柚希の演技からも抑えた中に温もりが伝わってくるし、娘役の美弥も愛情あふれる優しい目で母と我が子を見つめている。そんな積み重ねの結果、浮かび上がったのは「人生は美しい」という壮大な、しかしシンプルなテーマ。俳優たちの演技力と美しい音楽の力で、星々と小さな人間を対比させるような美しい情景が見えてくるようで、なんだか稽古の段階なのにすでに泣きたくなるような気持ちになってしまった。一方で、表舞台から退いている柚希演じる"ベラッジョ"が意を決して台詞を口にする、というような、劇中劇の外側の演出もつけられている。本番ではぜひそのあたりも注目してほしい。
その後、キャストが勢揃いし、この映画の真の目的が明かされるシーンへ。しんみり、じんわりした前のシーンとはうってかわって、"大・団・円!"といった賑やかさ。キャラクターたちの個性も際立っていて楽しい。柚希の"ベラッジョ"は言葉数は少ないながらもいつのまにか場の中心にいるような求心力があるのがさすがだし、ここまで少しひねた面も見せていた美弥の"ハロッズ"は映画愛を吐露し素直な表情を見せているのがチャーミング。セレブ設定の佐竹莉奈の"オルセー"も普通の女の子らしい明るい笑顔が可愛らしいし、"トキオ"役の鈴木瑛美子は返すたびに変わるコミカルなポーズも楽しく、イマドキの調子の良い女の子といった空気がぴったり。"ソーホー"宮本美季もまたインテリ風な台詞がハマっているし、フラメンコ劇団を率いているという"サグラダ"原田のパワフルさもこの人ならではの魅力だ。小林による"究極の当て書き"とでも言えるような役柄に、俳優たちがさらにその個性と魅力を注ぎ込み輝かせている。慣れ合わない、べたべたしない、しかしたまに意気投合して盛り上がることもある。何よりも仕事はきちんとやる女たち。それはこの登場人物たちの姿でありながら、きっとこのキャストたちの姿でもある。......もう「カッコいい!」としか言いようがない!!
さらに日替わりゲストが演じる"ノーウェア"の意外な正体も明かされ、ワチャワチャと賑やかな、そして女性らしい華やかな雰囲気も満開に。この日の稽古場には花乃まりあが参加。キュートで愛らしい"ノーウェア"をお茶目に演じていたが、柚希・美弥らとのコミカルな絡みなどはゲストによって内容も変わりそうで、必見だ。しかも、楽しいだけでなく昨今の世界情勢に目を向けるようなテーマ性もうっすら伝わってくるのが小林ワールドだし、映画ファンはそこここに潜む"映画愛"にも、ニヤリとするだろう。取材時は「SHOW-ism」の大きな魅力であるショーシーン、歌とダンスはほとんど見られなかったが、それでもこんなに見どころがいっぱい、キャストの魅力も溢れんばかり。すでに大満足の気分ではあるが、制作チームによれば「作中で撮影されるほかの短編映画には、男性役の柚希が美弥とのデュエットダンスを披露する、フィルム・ノワール風に描いた『常夜灯』や、殺陣を交えながらアクションや激しいダンスで踊り歌う『ハイヒールズ』など、それぞれ全くテイストの異なった5つのオムニバスに仕上がっているので、ぜひいろいろな角度から楽しんでいただけたら」とのこと。完成形を目にするのが楽しみである。
(取材・文:平野祥恵)
<公演情報>
11/20(日)~12/5(月) シアタークリエ (東京都)
<メイキング映像はコチラ!>