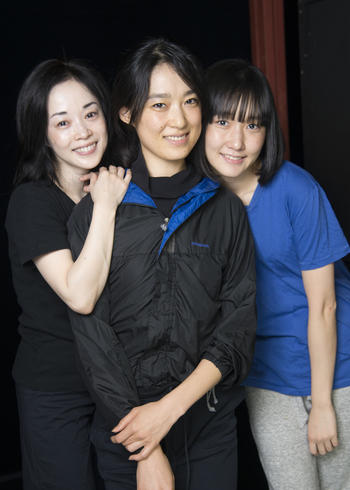高級娼婦という過去を持ち、36歳の若さで自ら人生を終えたカナダ生まれの女性作家ネリー・アルカン。彼女が残した4編の小説をコラージュし、カナダの演出家マリー・ブラッサールの手で舞台化されたのが、『この熱き私の激情~それは誰も触れることができないほど激しく燃える。あるいは、失われた七つの歌』だ。舞台に登場するのは6人の女優と1人のダンサー。ガラスで閉ざされた10の部屋のなかで各自がそれぞれのテーマを演じることで、ひとりの女性を表現するという演出がなされている。
その斬新な作品はどう形作られているのか。"神秘の部屋"の初音映莉子、"ヘビの部屋"の宮本裕子、"幻想の部屋"の芦那すみれが集まって、刺激的な稽古場の様子を語ってくれた。また、その言葉の数々が腑に落ちる稽古もレポート。演者自身が突き動かされているこの女性作家の"激情"は、実際の劇場空間でしか味わえない。
(宮本裕子さん、初音映莉子さん、芦名すみれさん)
◆インタビュー
【ひとりだけどひとりじゃない不思議な感覚】
──稽古も大詰めですが、今の手応えをお聞かせください。
初音「各自が別の部屋にいて、イヤモニ(イヤーモニター)でみんなのセリフを聞きながら演じているんです。だから、声だけが頼りというか。意識が声に集中するし、ひとりでいるけどひとりじゃない感覚もあるし。すごく不思議な体験をしている感じですね」
芦那「みんなで声を合わせなければいけないところはとくに、すごい集中力が必要なんです。うまくいかなくて止まっちゃっても、目を合わせることができないので、どこからもう一度始めるか、確認もできなくて」
宮本「その混乱期が長かったよね(笑)。でも、だからこそ、お互いがお互いを補い助け合うことに必死になって集中してると思います」
──声と心を合わせていく大変さがあるわけですね。片や、それぞれのソロではどんな表現を求められていますか。
芦那「トップバッターなので、マリーからは、とにかく冒頭からエネルギーをガツンと出してほしいと言われています。檻に閉じ込められた動物園の動物のように檻の中を行ったり来たりしながら、歳を取ること、肉体や美が衰えることへの恐怖や悲しみを爆発させる。初っ端が肝ですから頑張りたいです」
初音「私が語るのは、"自分の存在意義とは"という思いです。母親が男の子を望んでいたこととか、タロット占いで未来の自分が見えなかったことで、自分には先がないんじゃないかと思ったり。さらには、娼婦のときにお金を払う男性が世の主導権を握っていると実感して、男として生きていたらと思い描いたり。でも、なんで男だけが偉いんだ、女性にだって権利はあるはずだとネリーは疑問を抱いていて、私もそこはわかる部分があるので。強く表現していきたいなと思っています」
宮本「私が演じるのは、松雪(泰子)さんが"死"を表現したあとの、"ヘビの部屋"。ネリーが自殺した後に居る世界。マリーいわく、ここはニューストーリーになるそうなんです。心と肉体がバラバラな...。生きていた時を俯瞰で見てるような...。私が余分なものを入れると濁るような気がして。それに、マリーのネリーへの思いも感じますし、カナダですでに2度上演されていて、研ぎ澄まされている作品ですからね。ネリーの心に素直に触れるような感じで表現できたらなと思っています」
【聞いてると泣いちゃうセリフがある】
──ネリーという女性作家の言葉を、マリーさんの斬新な演出で立ち上げる舞台。観客にはどんな伝わり方をしそうでしょうか。
初音「ネリー・アルカンが書いた言葉を日本の土地で発するのは貴重なこと。彼女の考え、悩みをどれだけ自分のものにできるだろうと、私もそこに潜っているんですが。ただ、マリーはよく「直感を信じて」と言うんです。見えないものを信じてって。だから、観てくださるみなさんにも、ネリーの言葉を聞きながら、日常で忘れかけている見えないものとか、自分の信じているものとかが、ふわーっと浮かび上がってくるんじゃないかなと思うので。その漂う気配を感じてほしいなと思いますね」
芦那「私はまだ舞台が2本目なので演劇がどういうものかわかってないんですけど、でもきっと、観ている方も不思議な気持ちになる舞台になると思います。一人ひとりが各部屋に生息しててひとりでつぶやいていて誰かに向かって話してるという感じではない。なのに、いつしかその言葉が身近に感じられるという、不思議な空間になる気がします」
宮本「しかも、その言葉というのが、ここまで正直にさらけ出すのかと驚くようなものばかりでしょう。普通なら隠したい、見られたくないっていう恥部をネリーは書いている。だから、檻の中にいる私たちも、肉体的には洋服を着てるけど、裸になるより恥ずかしい何かをさらすことになるような気がする」
初音「私、聞いているといつも泣いちゃうセリフがあるんですよ」
宮本「泣かせるようなこと言ってないのにね。でも、文字を追ってるだけではわからなかったものがみんなの声で聞くと入ってくる。ネリーの痛みみたいなものが伝わってくる」
初音「そう、ピュアに響いてくるんです。きっとみなさんにもそんな体験をしていただけるんじゃないでしょうか」
芦那「全部は理解できなくても、1行だけでもぐさっとくるような言葉があるでしょうし。そんな言葉と出会えるというのはとても豊かなことだと、私は思います」
宮本「これはわかると思える感情に触れられるとかね。だから、生きてるだけですばらしいよと思えるところが、この作品にはあるような気がするんです」
◆稽古場レポート
【10の部屋で紡がれる鮮烈な言葉】
2段に組み立てられた10個の部屋が圧倒的な存在感を放つ稽古場。稽古前のインタビューに応じてくれた初音、宮本、芦那が上段の3部屋にいる。そして下段には、死の魅力を語る"影の部屋"の松雪泰子、宇宙と自然について語る"天空の部屋"の小島聖、死んだ姉や家族、血縁のことを語る"血の部屋"の霧矢大夢。ダンサーの奥野美和は、どの部屋へも出入り自由で、すべての女たちと絡んでいく設定だ。部屋の前面は本番ではガラス戸で閉じられるが、仮のセットからでもその閉塞感は伝わってくる。女優とダンサーがそれぞれの部屋にスタンバイした。
稽古は、2つの場面をおさらいするところから始まった。いずれも、何人かで声を合わせて語るところだ。途中歌う人物もいる。流れているのは前衛的な音楽。わかりやすいメロディーがないだけに、どのタイミングで語り始め、どのタイミングで動くのか、非常に掴みづらそうである。演出のマリーがこだわっていたのも、音に合わせて動くこと。誰かが立っているときに誰かが倒れ、誰かがだんだん身体を崩していく。そのダンスとも言えない、いびつだけれど何とも美しい身体表現に、まず心を奪われる。
「みなさん、よい通しを!」のマリーの声で始まった通し稽古では、さらに"声"が際立った。冒頭の合わせて語るところでは、呼吸をひとつにしながらも個性の違いが重層的な奥行きを感じさせる。一人ひとりの語りが聞かせる心の叫びにはまさに意識を集中せざるを得ない。
身体を揺らしながら想像以上の爆発力を見せた芦那。
ダンサー奥野とのスタイリッシュな絡みが逆に女である悲しみを伝える初音。
地の底からの呻き声にも聞こえる宮本。
それぞれの女優の言葉が突き刺さる。「あなたはこの痛みに気づかないふりをしてるだけじゃないですか」と。
宮本が語っていたように、女優たちは自分の奥底にあるものを絞り出すかのごとく表現している。耳を、心を研ぎ澄まして、それを受け止め自分を見つめ直す。こんな贅沢な時間はないだろう。
(写真:川野結李歌 / 文章:大内弓子)