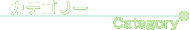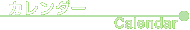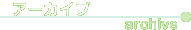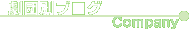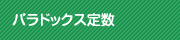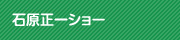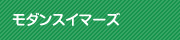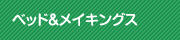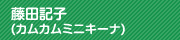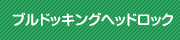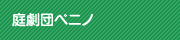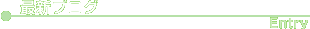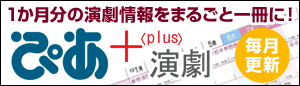キャラメルボックスの鍛治本大樹さんが気になる公演をチョイスして、稽古場からレポートをお届けする不定期連載【鍛治本大樹の稽古場探訪記】。
第2回目はベッド&メイキングス『こそぎ落としの明け暮れ』です。
都内某所。
富岡晃一郎さんと福原充則さんが立ち上げた、ベッド&メイキングスの最新作『こそぎ落としの明け暮れ』の稽古場にお邪魔した。

作・演出を担当する福原さんの第62回岸田國士戯曲賞受賞後、初の長編書き下ろし作品ということで僕自身、注目していた舞台だ。
ベッド&メイキングスは、『墓場、女子高生(再演・2015年)』が初見だった。個性的な女優陣の魅力がこれでもかと引き出されてぶつかり合っているのが印象に残っている。
稽古場の感想を書く前に、ぜひとも脚本について触れておきたい。
今回、稽古場をレポートするにあたり、事前に脚本を読ませて頂いた。
もちろん新作なのでネタバレは出来ないが、全体的な展開もさることながら、一つひとつのやりとり、一人ひとりのセリフ、言葉ひとつとってもそのどれもが面白い。
決して大袈裟ではない"言葉たち"が、福原さんの手にかかるとまるで魔法にでもかかったように絶妙な掛け合いとなって、何度もムフフと笑ってしまった。
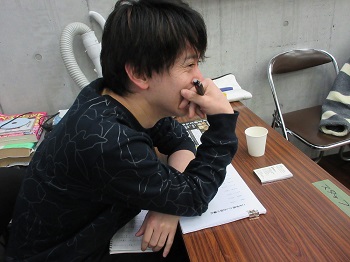
役者として台本に向かう時、僕が心掛けている事がある。
それは「脚本(台本)とは、設計図である」ということ。
ある程度の造形の指針、骨格が書き記されてはいるけど、どんな素材の建材で立てるのか、そこにどんな壁紙を貼るのか、どんなインテリアを置くのかは、ひとまず役者に委ねられているであろうし、腕の見せどころだと思っている。
ところが、福原さんの書く脚本は、素材、色、インテリアまで指定されているような、完成写真を見せられているかのような緻密さで、読み手(役者)に迫って来る。
セリフを発する時の、声の大きさ、トーン、リズム、息遣い、テンポの正解が台本を開くだけで飛び出してくるような感覚。
これは面白い脚本である証でもあるけど、役者目線でいくと手強いなぁ......。
そんな印象を持って稽古場へと足を運んだ。